今日はカレイについて書きたいと思います。
なんでカレイ?と思ったかもしれませんが、今日はカレイのこと書くと決めましたので書きます。
カレイを知らない日本人はいないと思います。
日本においてカレイは有名魚ですが、ダイビング中、頻繁に登場する魚ではありません。
カレイは「バランス感覚に優れた砂泥底の忍者」とも呼ばれているので、岩礁域をメインに潜るダイビングスポットには分布しないからでしょう。
昨今行われている水中写真コンテストの入賞作品にカレイの写真は100%出てきません。
(個人的にはメジナを被写体にした優秀作品が見てみたいです)
カレイの生態についてもダイバーはほとんど知りません。
(生態を一番知られている魚はクマノミだと思う)
まず「両眼が表側にあるもの」を総称して「カレイ目」と言います。
カレイ目は、「カレイ亜目」と「ウシノシタ亜目」に分けられます。
カレイ亜目には、「カレイ科」、「ヒラメ科」、「ダルマガレイ科」「コケビラメ科」などがあります。
「両眼が右」にあるカレイ科は世界で100種、日本で40種ほど生息しています。
カレイ科は種類数、個体数が多く、カレイ目の中では最も重要なグループです。
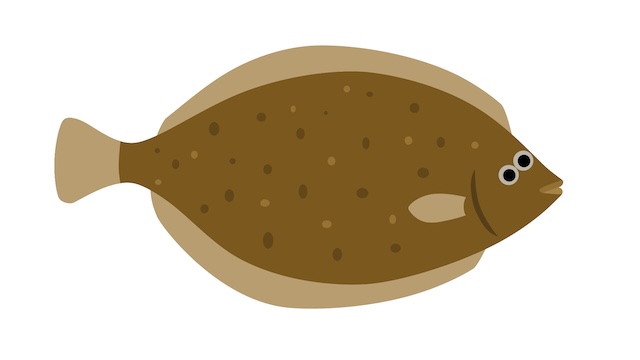
カレイ科は「カレイ亜科」「カワラガレイ亜科」「ベロガレイ亜科」「ミナミガレイ亜科」に大別されます。
その中でも「カレイ亜科」はカレイ科の主流で「60種類」ほどいます。
カレイ亜科以外の仲間は日本近海にほとんど生息していません。

カワラガレイ亜科→世界に13種ほど。主に熱帯地方に生息。カワラガレイが有名。裏側の側線が退化している
ベロガレイ亜科→世界で14種ほど。10センチそこそこの小型種。主に熱帯地方に生息。せびれが眼の前縁よりも前からはじまるのが特徴
ミナミガレイ亜科→世界で12種ほど。南半球に生息。頭や形がウシノシタ類に似ている。左右のはらびれが不相称で表側のものがよく発達しておりしりびれと連絡すること。側線が両体側ともよく発達すること。

カレイ亜科は太平洋、大西洋、北極近くから温水域にかけて分布しています。
(暖流の影響が著しいところには分布しません)
太平洋では西は台湾あたり、東はカリフォルニア。
大西洋では西は北緯44度付近、東はジブラルタル海峡。
日本沿岸ではオヒョウ、スナガレイ、ツノガレイは北海道南部。
アブラガレイ、マツカワ、メダマガレイ、ババガレイなどは銚子付近が南限。
日本の中部、南部まで分布しているのは、
ムシガレイ、サメガレイ、ヤナギムシガレイ、メイタガレイ、マコガレイ、イシガレイ、クロガシラガレイ、ババガレイ、スナガレイ、ヌマガレイ、ソウハチ、マガレイ、ホシガレイなどです。

カレイの仲間は視覚、嗅覚、味覚、側線感覚がバランスよく発達しています。
側線はまわりの水の動きや水圧の変化を受け取るとともに周波数の低い音も感知します。
カレイの仲間は周囲に起きた小さな水の動きに敏感なことは、触手を絶えず動かすイソギンチャク、菅の中に住む多毛類、呼吸のために水を出し入れする水管を備えた二枚貝を好んで食べることで理解できます。
カレイの主なエサですが、水底にすむ魚、二枚貝、巻貝、イカ類、エビカニ、アミ類、多毛類、ヒトデなどです。
大きな口と鋭い歯をもつオヒョウは魚食性。
口が大きいアカガレイ、ソウハチ、ムシガレイ、ヌマガレイはエビカニ、二枚貝、巻貝、多毛類、ヒトデ、小魚。
口が小さく歯が裏側のあごにあって未発達なマガレイ、マコガレイ、ババガレイ、ヒレグロなどは運動性の弱い多毛類、貝類、エビカニとなります。
エサを食べる時間は「1日2回の盛期」があります。
例えば、
ムシガレイは10時と18時。
マコガレイは8時と15時から夕刻。
マガレイは9時と15時。

カレイは住み場を変えます。
産卵期になると岸近くに移動し、産卵が終わると深場、または餌の多い低水温域に移動します。
産卵→餌取り→越冬のために移動することを「回遊」と言いますが、30センチくらいの中型カレイでも100km以上移動します。
大型のカレイ、オヒョウはアメリカ西岸の水域へ南下して、水深300m~400mの深層で産卵し、生まれた幼魚は北を目指します。若魚はアラスカやアリューシャン列島の周辺海域まで移動します。
成熟が始まるまえに次第に南下回遊が始まり1600kmも離れた産卵場に移動するものもいます。
すごいですよね。

カレイの産卵時期ですが、本州の北、中部海域では晩秋から初夏です。
北海道またはそれ以北の海域では冬から夏です。
本州沿岸
アカガレイ、マツカワ、メイタガレイ、イシガレイ、マコガレイなどは晩秋から3月ごろ。
ソウハチ、ヌマガレイ、マガレイ、ババガレイ、ヒレグロは2月から4月ごろ。
北海道
マコガレイが2月から4月ごろ。
アカガレイ、イシガレイ、マガレイなどは4月から6月ごろ。
オヒョウが5月から6月ごろ。
ソウハチ、ヒレグロなどは6月から8月ごろ。
※北海道は産卵時期が遅くなるんです。
オスメスの割合いですが、若魚ではオスが多く、老魚になるとメスが多くなります。
アカガレイ→3歳までオスが多いが、5歳上でメスだけになる。
ソウハチ→生まれたときはオスが多く、1歳でオスメスが同数になり、4歳でメスしかいない。
イシガレイ→5歳を超えるとオスはいなくなる。
それゆえオスは早熟で、メスよりも1年以上も早く成熟します。
一生を通じての成長状態は幼魚の時代は成長が遅く、同年代でもメスの方がオスより多少成長がいいです。
メスの寿命は小型種で数歳、中型種で10歳、大型種で15歳、超大型種は40歳まで生きた記録があります。
魚類の中でも長命の部類に入ります。
残念なことにオスの寿命はメスより2年から数年短いです。
最後にカレイの地方名ですが、日本海ではアサバが総称になります。
一般的には浅羽と書かれますが、体が薄いという意味の薄羽から来ていると言われています。
というわけで、次回はカレイの味について書いていきたいと思います。
それは釣れたあとのおはなしになりますが。
RIO


